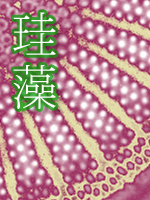琵琶湖博物館 WEB図鑑「珪藻」
Nitzschia inconspicua Grunow









 10μm 10μm
|
| A: 大和川支流佐保川(奈良県) |





 10μm 10μm
|
| B: 大分川(大分県) |
- 学名
- Nitzschia inconspicua Grunow, Verh. K. K. Zool. -Bot. Ges. Wien 12: 579. pl. 18, f. 25. 1862.
- 基礎異名
- その他異名
- Nitzschia frustulum var. inconspicua (Grunow) Grunow in Van Heurck 1881.
- 和名
- 類似種との区別点
- Nitzschia hantzschiana の小型個体と区別し難いことが多いが,条線を構成する胞紋列がより粗い。また電子顕微鏡で観察すると,条線は縦溝付近で二叉していない。Nitzschia frustulum と本種を分ける明確な規準はないが,小型個体 (ほぼ 20μm 以下) ばかりからなり,殻形が楕円形に近い個体群を本種とした。
- 報告があった場所
- 汎世界種 (Krammer and lange-Bertalot, 1988)。日本でも Nitzschia perpusilla,Nitzschia frustulum などとして報告されていることが多いようである。
- 生態情報
- 好アルカリ性 (渡辺ら, 2005)。電解質が中程度あるいは多い,α-β-中腐水性の境界までの水域に生息する;波打ち際に多い (Krammer and Lange-Bertalot, 1988)。有機窒素を利用できる (Van Dam et al., 1984)。淡水域では本種の方が Nitzschia frustulum よりも普通のようである。