

 |
 |
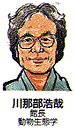 琵琶湖博物館では「湖と人間」というテーマにそって、研究・調査、交流・サービス、収集・保管、情報、展示など多彩な活動を展示していきます。ここではその一つである常設展示の概要とその担当者を紹介します。
琵琶湖博物館では「湖と人間」というテーマにそって、研究・調査、交流・サービス、収集・保管、情報、展示など多彩な活動を展示していきます。ここではその一つである常設展示の概要とその担当者を紹介します。
| A展示室 琵琶湖のおいたち |
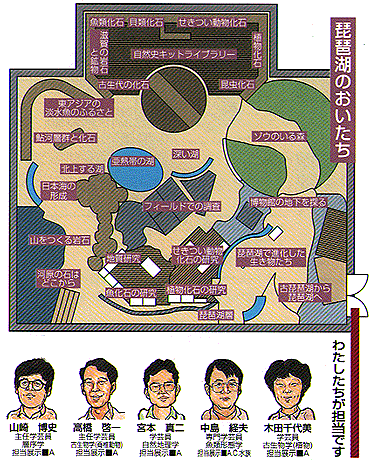 展示室へのエスカレータをのぼると湖岸に生えるヨシの風景が見えてきます。ここが最初の展示室。入ると、足元には河原の石ころがあります。宝石のような輝きはありませんが、そこには滋賀の大地がどのように形成されたのかが秘められています。
展示室へのエスカレータをのぼると湖岸に生えるヨシの風景が見えてきます。ここが最初の展示室。入ると、足元には河原の石ころがあります。宝石のような輝きはありませんが、そこには滋賀の大地がどのように形成されたのかが秘められています。
河原の風景をぬけると、亜熱帯の気候の中でワニや大型のコイが泳いでいるジオラマが見えます。約380万年前にあった、浅くて小さな琵琶湖の原型です。今の位置から50kmも南にありました。
約200万年前の古琵琶湖のようすは、紅葉したメタセコイアの森のジオラマで体感できます。森が湿地に移り変わるあたりには、小型のアケボノゾウの親子がいます。
博物館の地下920mを掘ったボーリング調査の展示を見て、展示室の中央部に進むと、そこはフィールド調査や研究室の再現です。展示は、このような研究の成果をもとにつくられました。
もっと化石や岩石を見たい人には、展示室の1番奥にあるコレクション・ギャラリー「中・古生代の化石と岩石」「古琵琶湖層群の化石」でゆっくり楽しんでいただけます。
| B展示室 人と琵琶湖の歴史 |
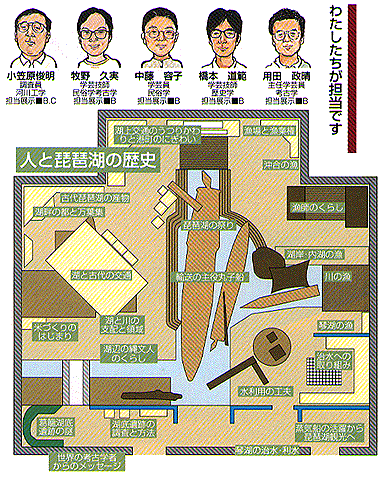 この展示室では、人びとが琵琶湖の周辺に住み着いてから戦前までの人と琵琶湖の関わりの歴史が展示されています。
この展示室では、人びとが琵琶湖の周辺に住み着いてから戦前までの人と琵琶湖の関わりの歴史が展示されています。
琵琶湖は古くからさまざまな形で人びとに利用されてきました。私たちはその知恵と技術を、遺構や遺物、先人たちの残した数々の道具や古文書・絵図、伝承といった形で目にすることができます。
世界最大の淡水貝塚である粟津貝塚の発掘現場を再現した展示では、セタシジミやコイなどの食料資源が縄文時代から利用されていたことがわかります。それぞれ原寸大で復元した瀬田唐橋の橋脚基礎部や百石積の丸子船は、琵琶湖が日本の東西南北を結ぶ交通の要所にあったことを示すものです。エリ、ヤナといった仕掛けやモンドリ、タツベといった漁具・漁法に見られるように、琵琶湖の魚は大事な食料資源であり、またしばしば漁場争いの種ともなりました。
もちろん生活用水としての重要性はいうまでもなく、井戸、水車のほか竜尾車といった道具で水が利用されました。一方、西野水道やオランダ堰堤に見られるように、水利用の歴史は同時に水との戦い歴史でもありました。 忘れられつつあるかつての人と琵琶湖の関わりとその深まりの歴史をふり返ってみてください。
 |
 |
 |