

 |
 |
館長対談
 |
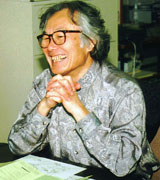 |
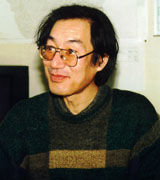 |
|
朽木いきものふれあいの里 |
琵琶湖博物館 |
琵琶湖博物館 |
川那部■一面の雪景色ですね。
来見■生きものに触れ合うにも、なかなか良い季節ですよ。この施設は、展示もしていますけれども、周りにある自然とその見かたの紹介が主です。まずはこれを足に付けて、そのへんをご一緒に歩き回りましょう。今朝も、動物どうしのあいだに起こったあるイヴェントを見つけましたから。
川那部■和かんじきですね、これを着けるのは久しぶりです。新雪の上をこれで歩くと、ほんとうに気持が良い。
来見■このあずまやのところです。ほら、向こうからネズミの足跡が来ているでしょう。あそことここの腰掛けの下で二度方向を変えて、そこで手すりにいったん跳び上がって、降りてすぐにまた、鋭角に方向を変えている。そしてここで大きく跳びはねて、その次は消えている。こちらから来ているのはキツネですね。ここで交わって、あとはキツネの足跡だけが向こうへ続いている。こういう劇的な状況もここでは、注意しているとときどき見られるのです。
|
布谷■「朽木いきものふれあいの里」は、全国にいくつかあるものの中でも最も初期につくられた施設で、全国のモデルになっています。来見さんはここで、ずいぶんいろいろな観察会や事業をやっておられるのですね。 来見■私はここでは指導員と呼ばれているのですが、もう一人の指導員と所長との三人でやっています。それぞれの性格を生かした活動でして、観察会のテーマも、毎回違います。自然は全体としては同じでも、旬のものを味わうのが一番なわけで、したがって個々の内容や見る角度はいつも違うわけです。観察会はお客さんあってのものですから、良い反応があればやっぱり楽しいですし。言いかえると、「お客さんと指導員の展示」に近いんです。 川那部■はははは。人間どうしの「関係」の展示ですね。 布谷■最近は、環境教育が大切だと言う意見を良く聞きます。ところが何をしているかというと、動物愛護やゴミ集めであったり、そうかと思うといきなりオゾンホールや世界規模の環境破壊の話になったりして、自分の生活と結びつくところがわかりにくい。それはきっと身近な自然を意識したくらしができていないからだろうと思うんです。自然と離れたところで自然について論じても無理がありますよね。その点ここでは「生の自然」があるからこそできるような、そう言ったプログラムを進めておられますね。 来見■環境教育では確かに、「生の自然」も大事です。でも、それ以上に「生の人間性」とでも言いますか、人間の生きかたみたいな部分がいちばん大切じゃないかと、私は思うんです。自分で物事を決定し、判断して行動するような力、それができていないと、どんなに技術がわかったとしても、自分の身の周りの環境問題を解決することは、できないのではないでしょうか。 昔の人は、自然の中でちゃんと生活して来たわけですよね。年とった人々は、いまの子どもやらよりはよっぽど生の自然に親しんで生きてきたはずです。しかし、その大人たちが環境問題を起こしました。そして、自然を知らない子どもたちが、それを解決せなあかんわけでしょう。だから、どうして問題が起こったのか、どこが間違っており、足りなんだのかと言うことをしっかり考えて、つくり直して行くかが環境教育やろうと思うんです。口幅ったいですけれども。 川那部■いやいや、素晴らしいことです。自然観察自体も、自然のことだけではなくて人との関係から入って行かなければならないと言うのが、本当です。 |
「これはシカですね。」と木についたマーキングを指さし、ていねいに説明をしてもらいました |
川那部■来見さんは、このあたりの出ですか。
来見■いや、徳島生まれの大阪育ちで、それから大津、そしてこの近畿のいちばん北まで北上して来たのです。滋賀大を選んだのは、横に瀬田川があって、毎日釣りができるからでした。
川那部■そのときの魚は、どうしました?
来見■友だちと二人で、みんな食べました。食べんとわからんと思うんですよ、魚のことは。「殺すのは可哀相や」と言うので、放す人がこの頃多いけれども、鰓(えら)が傷ついたり、鱗(うろこ)や粘液がやられて、大部分は結局死んでしまいます。だいたい、命を玩(もてあそ)ぶのは良くないことで、食べると命がつながるのではないでしょうか。それに全部食べようと思えば、たくさんは釣りませんし。
川那部■その意見は、大賛成ですね。
布谷■このあたりは、自然が豊かなだけではなくて、地元の朽木の人や集落自体が元気ですね。ここの施設は「自然観察施設」ということになっていますが、本当に多くの人が望んでいるのは、おそらく自然を見ることだけではなくて、この朽木という集落に昔からくらしてきた人達がつくり出してきた、自然とその自然を活用したくらしぶりだろうと、思うんです。 各地で行なわれている自然観察会も、自然だけを観察するのではなく、人のくらしとの関係を考えるような方向にかわりつつありますね。いまの来見さんのお話のように、地元の文化などが観察会にうまく生かされると、いっそう面白い展開ができると思うのですが、そのあたりはいかがですか。
来見■そう言うこともありますね。また逆に村にとっては、他所からたくさんの人がここの自然を楽しみに来るということ自体が、良い状態になるのです。自分らにとっては「あたりまえ」のものなんやけど、それがものすごく価値があるらしい、というのが、はっきりわかるわけです。
そして、あたりまえの自分たちの生活が、これまた実はものすごい意味があるんやとそんなこともわかって来て、自信をもってやって行けるのです。それぞれ工夫して、ここをちょっと変えようかなどと思いながらやると、もっと楽しくなりますし。
 |
| 「雪上の小動物の足跡から、いろんな想像をするのが楽しいんですよ」と来見さん |
川那部■琵琶湖博物館は、「ほんものは琵琶湖とその周り」であって、建物のなかにあるのは「その入口」と言う考えなのですが、あの大きさになると、それを本格的に示すことはなかなかたいへんです。そういう点ではここは、小さいことをむしろ積極的に活かして、みごとにやっていらっしゃる。そこは、たいへん羨ましいところでもあります。
来見■ええ。中の面倒はあまり見なくても良いと言うのが、却って良いんです。こういう小さい建物には、人がおったらそれで良いんですよ。その人を訪ねて来る人があって、その人のそのときの考えで説明しながら、自然と触れ合って貰うのです。
川那部■本当にそうですね。この「ふれあいの里」は、博物館とは呼ばれていませんが、考えかたとしては共通したところが多いですね。琵琶湖博物館も、ここのようないろいろな施設を使わせていただくことを考えないといけません。
布谷■そうなんです。ここでならばできるけれど、琵琶湖博物館ではできないことも多いんです。県内には、ここの他にもいろいろな施設がありますから、ネットワークをつくって行きたいと思っているんです。
来見■ここはわりと、森林がしっかりしているでしょう。落葉の層も厚いですし。それで奥のほうには、イノシシの「ぬた場」になっている場所なんかもあって、雨が降らなくっても水があります。つまり、「このあたりから川が始まっている」というような場所が、何カ所かあるのです。そこからずっと降って、琵琶湖まで下りていくと、川の仕組みが結構良くわかります。こういうことは、一緒にやると面白いことになりそうですね。これまでは、上流の部分はここで実際に見ても、下流や琵琶湖自体のことは、お話でやっていたんですけれども。
布谷■ぜひこれから、一緒に事業をやらせていただければ良いなと思います。今日は貴重なお話を聞かせてくださって、有難うございました。
川那部■和かんじきで歩きながら、お話ができて、とくに有意義でした。帰りには温泉、たしか「朽木温泉てんくう」と言う名前でしたね、あそこへも入れて貰って来ます。
*ぬた場:本来の意味は沼地や湿田などをさすが、一般的にはイノシシが体についたダニなどを落とすために、転げ回ってどろあびをする場所を指すことが多い。
 |
 |
 |